木造住宅について
木造住宅の世界では、経験と勘で「構造」を考えてきた歴史があります。
木造住宅の建築は、詳細な計算(構造計算:許容応力度計算)までは行われていないことが多い。
その理由については以下のことが考えられます。
・建築基準法でも、木造の家は手軽に建築できると考えられていて、構造安全性確認についての規定が少ししかない
・建築士や施工者の大半が構造計算によって安全性を確認する意識が低い
・構造計算書の提出が義務化されていない
など
確認申請OK≠安全
確認申請が通れば、建築基準法を満たしていると思ったら大間違いです。
500㎡未満の木造2階建てまでの一般的な家は、建築士が設計しているため、確認申請時に構造計算書の提出義務がありませんでした。
当然、計算が間違っているかをチェックされないし、計算しなくても建築できてしまいます。
それどころか、構造計算ができなかったり、そんな法律の規定があることすら知らない建築士もいるのではないでしょうか。
そのため、確認申請適合でも構造チェックがされていないため、建築基準法に適合しているわけではないことを知っておきましょう。
木造の構造検討
検討項目は3種類あります。
①壁量の検討・・・地震や台風で家が壊れないように計算すること
②部材の検討・・・骨組みである柱や針の組み方やサイズを決めること
③地盤・基礎の検討・・・地盤調査し、基礎の形状を決めること
↓①壁量の検討はこちら
計算の方法
計算の方法も3種類あります。
①仕様規定・・・建築基準法(木造2階建てまで)
②性能表示の計算・・・品確法
③許容応力度計算・・・建築基準法(木造3階建て)
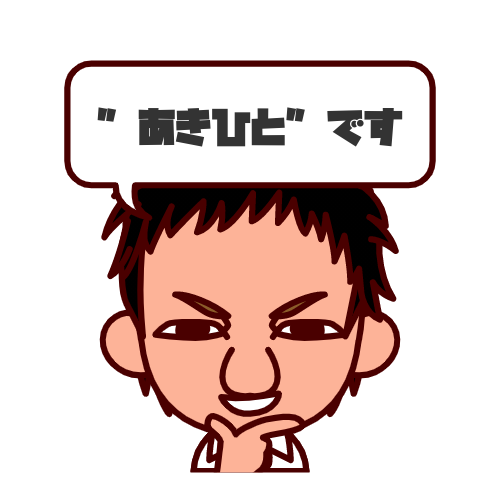
ちょっと物足りないけど、①仕様規定を満たすことが最低条件です。
↓①仕様規定の検討はこちら
まとめ
木造住宅の構造について紹介しました。
近年では1995年の阪神淡路大震災を受けて、2000年に法改正され、木造建築物の仕様規定(構造安全性に関する最低限のルール)が大きく変わりました。
2025年に法改正され、仕様規定の審査が開始されます。
↓法改正の内容はこちら


